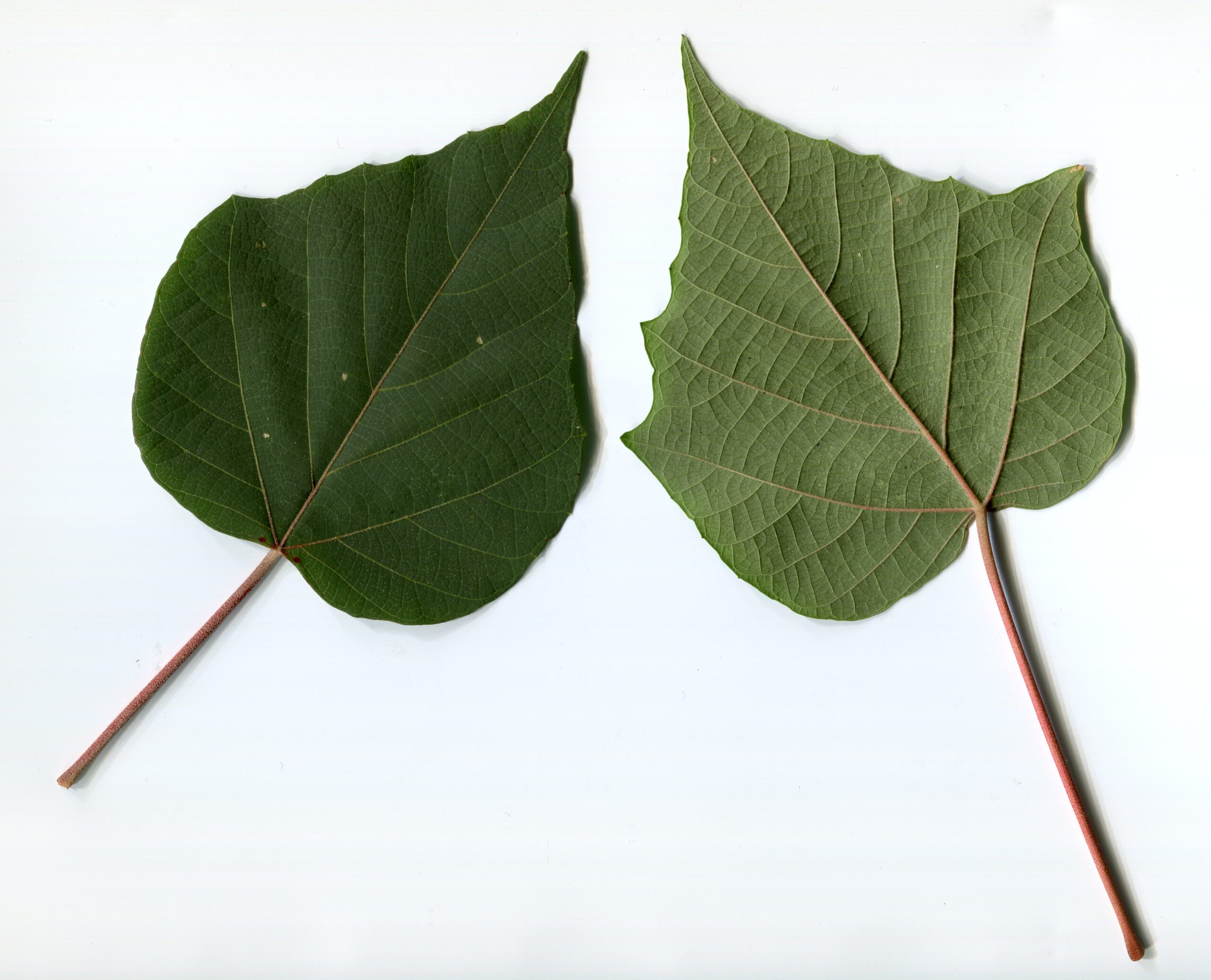基本情報
- 学名:Rhododendron degronianum
- 科名・属名:ツツジ科ツツジ属
- 漢字名:東石楠花
- 別名:シャクナゲ(石楠花)
名前の由来
- 「アズマ」は、東日本に多い
- 「シャクナゲ」は、漢名「石南花」を呉音(ごおん)読みした「しゃくなんげ」が転訛したものだが、「石南花」は、本来バラ科のオオカナメモチで誤用
生育地
- 山地~深山の岩場や礫の多い林内や林縁
樹形
- 落葉低木
樹皮
- 灰白色
葉
- 葉序:互生、枝先に集まってつく
- 葉形:長楕円形、葉身長7~17cm
- 葉縁:全縁、裏側に巻く
- 葉脈:主脈が目立ち、側脈は目立たない
- 質感:厚く革質、表面は光沢あり、裏面は淡褐色の軟毛が密生
- 葉柄:1~2.5cm
花
- 性: 両性花
- 花序:枝先に散房花序、淡紅紫色~紅紫色の花が3~12個つく
- 花被:花冠は直径4~6cm、漏斗状鐘形、上部は5裂、花柄の長さ1.5~3cmで縮れ毛あり、雄しべ10個、雌しべ1個
- 開花期:5~6月
- 送粉方法:虫媒
果実
- 種類:蒴果、熟すと縦に裂ける
- 形:長さ1~2.5cmの円柱形
- 色:褐色?
- 成熟期:7~10月?
種子
- 数:多数
- 形:細長く小さい
- 色:‐
- 散布方法:風散布
冬芽
- 鱗芽
- 花芽は長さ2.5cmほどで枝先につく
葉痕
- 形:‐
- 維管束痕:‐
用途
特記事項
参考
- スタンダード版 APG牧野植物図:[2-3051]
- 新牧野日本植物圖鑑:[2151]
- 山渓ハンディ図鑑 樹に咲く花:[3-98P]
- 山渓ハンディ図鑑 増補改訂 樹木の葉:[609P]
- “しゅんさん”の観察した静岡県の樹木:[下275]
- 観察と発見シリーズ 樹木博士入門:[‐]
- 「読む」植物図鑑:[‐]
写真
以下には他種(セイヨウシャクナゲ?)が混ざっている。