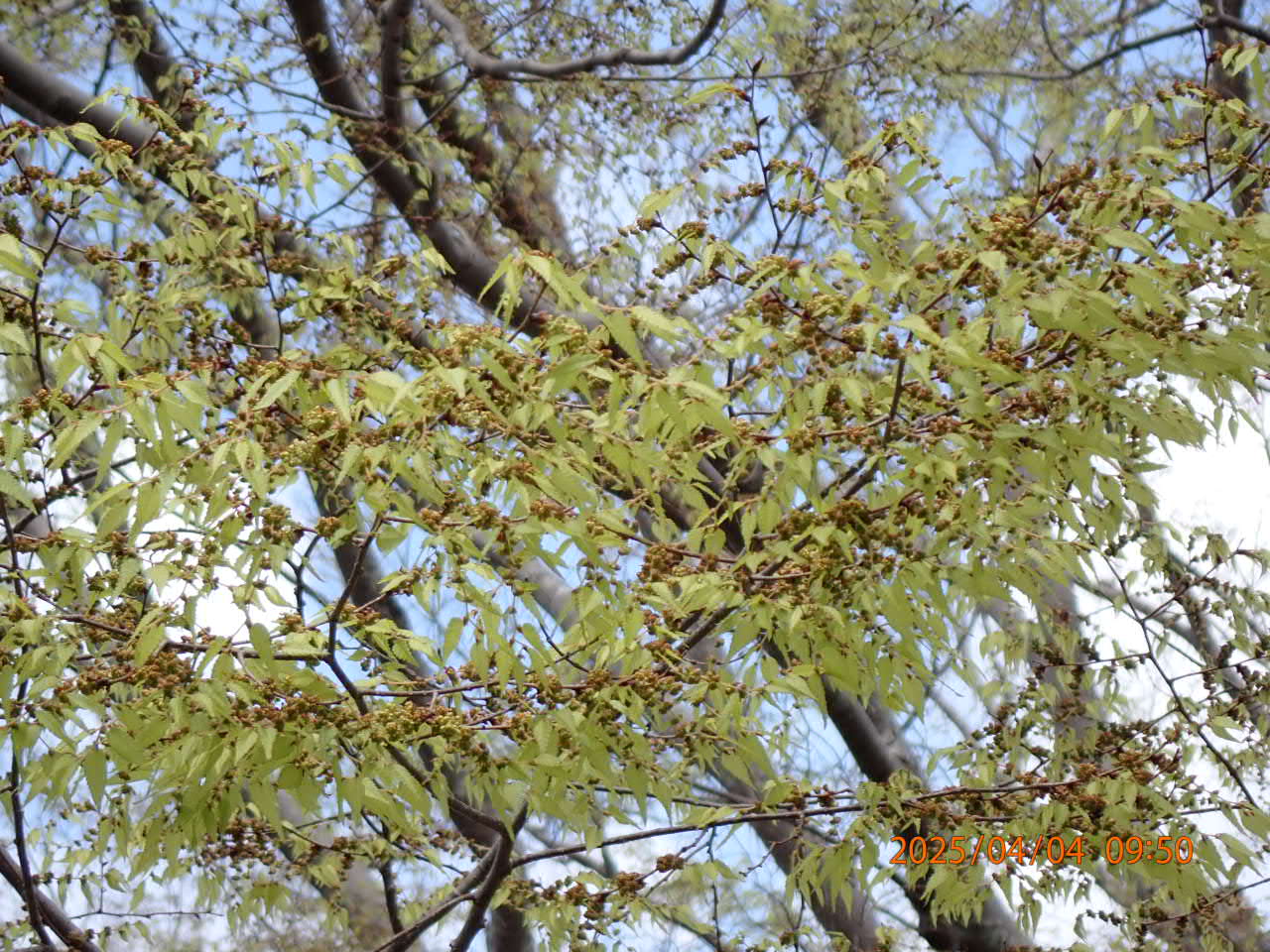基本情報
- 学名:Juniperus rigida
- 科名・属名:ヒノキ科ビャクシン属
- 漢字名:鼠刺
名前の由来
- ネズミの穴にこの葉を詰めておくと痛いのでネズミの害を防ぐ
生育地
- 丘陵~山地。砂地や尾根などのやせ地
樹形
- 常緑小高木
樹皮
- 灰色を帯びた赤褐色。薄くはがれる
葉
- 葉序:3輪生
- 葉形:針状。長さ10~25mm。先は鋭くとがり、触れると痛い
- 葉質:表面に溝があり、白い気孔帯が1本あり
花
- 花性: 雌雄異株
- 花序:前年枝の葉腋につく
- 雄花:長さ4~5mmの楕円形で黄褐色
- 雌花:先のとがった鱗片3個
- 花被:無花被花(花冠と萼なし)
- 開花期:4月
- 送粉方法:風媒
果実
種子
- 種類:球果
- 形:直径8~10mmの球形で液果状
- 成熟期:翌年または翌々年の10月頃。緑色→黒紫色。白いロウ質におおわれる
- 果鱗(種鱗):肉質で完全に合着し、裂開しない(ビャクシン属)
- 種子:長さ4~5mm。表面に樹脂のかたまりあり
- 散布方法:動物(鳥)散布
冬芽
葉痕
用途
- 材:芳香があり、以前は「和白檀(わびゃくだん)」といって、装飾用の柱や器具などに白檀(香木の一種)の代わりに用いた
- 盆栽:杜松(としょう)
- 果実:球果を乾燥させたものは生薬の「杜松子(としょうし)/杜松実(としょうじつ)」と呼び、利尿、尿道炎、リュウマチ、神経痛などに用いる
特記事項
参考
- スタンダード版 APG牧野植物図:[1-49]
- 新牧野日本植物圖鑑:[67]
- 山渓ハンディ図鑑 樹に咲く花:[3-644P]
- 山渓ハンディ図鑑 増補改訂 樹木の葉:[82P]
- “しゅんさん”の観察した静岡県の樹木:[上23]
- 観察と発見シリーズ 樹木博士入門:[‐]
- 「読む」植物図鑑:[‐]