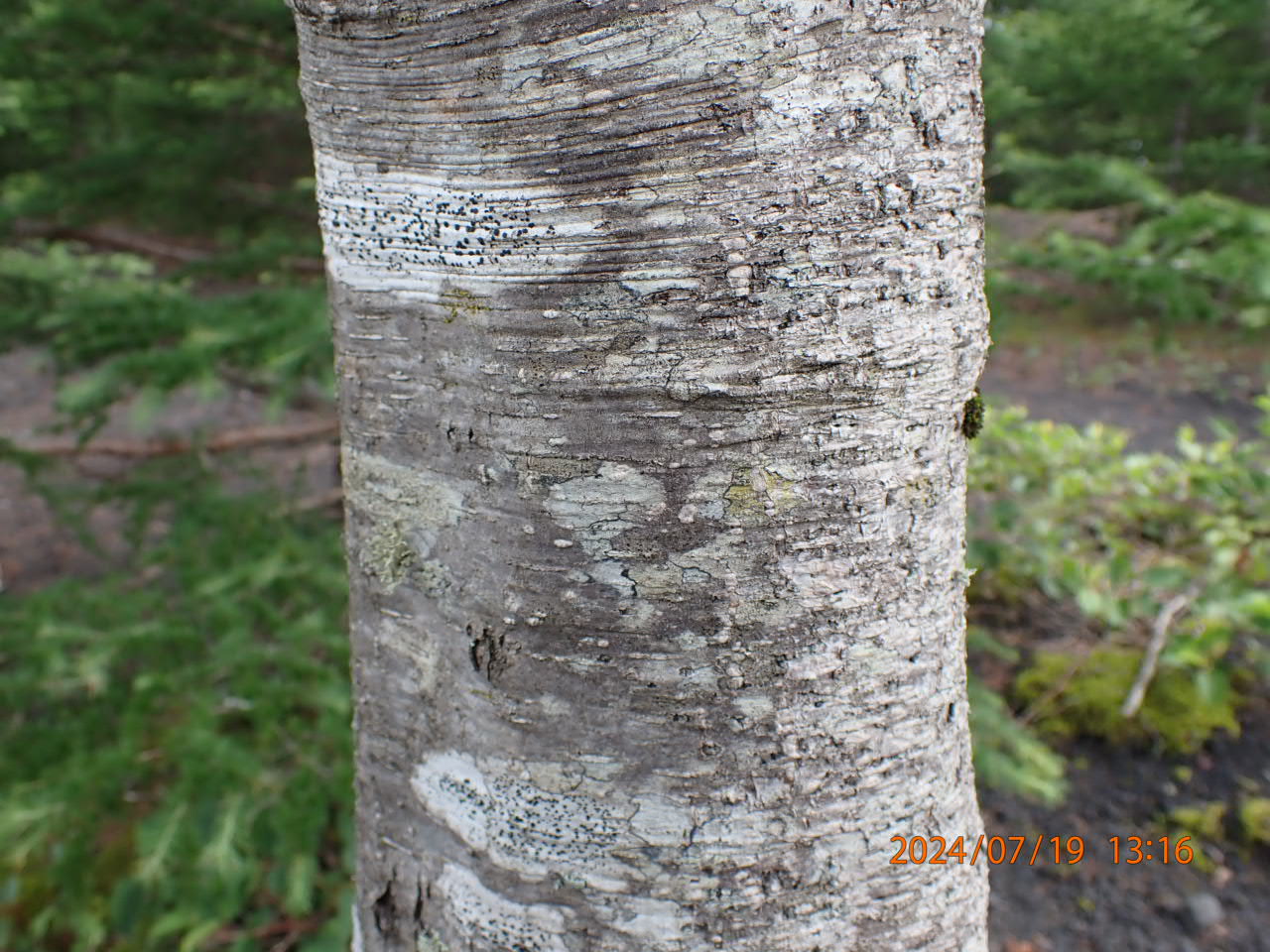基本情報
- 学名:Alnus matsumurae
- 科名・属名:カバノキ科ハンノキ属
- 漢字名:矢筈榛の木
名前の由来
- 「ヤハズ(矢筈)」は、葉の先端のちぎったように凹んだ形を矢筈に見立てた
- 「ハンノキ(榛の木)」は、ハンノキの名前の由来参照
生育地
- 日本固有種
- 山地の上部から亜高山帯。多雪地帯の崩壊地や沢沿いに多い
樹形
- 落葉高木
樹皮
- 灰黒色。なめらかで、横長の皮目が多い
葉
- 葉序:互生
- 葉形:広卵形、葉身長5~10cm。先は深く凹む
- 葉縁:不ぞろいの浅い重鋸歯
- 葉脈:側脈6~9対、裏面で隆起
- 葉柄:1.5~3cm
花
- 花性: 雌雄同株/異花
- 花序:
- 雄花序:枝先に1~2個下垂、有柄
- 雌花序:雄花序の下方に2~5個総状に集まってつく
- 花被:単花被花(花冠なし雄花に萼のみ)
- 雄花:苞のわきに3個つく
- 雌花:苞のわきに2個つく。花柱は紅色で2裂
- 開花期:4~5月、葉の展開前
- 送粉方法:風媒
果実
- 種類:堅果が集まった複合果
- 形:果穂は長さ1.5~2cmの楕円形
- 果鱗:長さ4~5mmの扇形
- 成熟期:10月?
種子
- 数:堅果は2個、果鱗の内側につく
- 形:堅果は長さ3mmほどの扁平な広楕円形、頂部に花柱が残り、両側に幅約0.5mmの翼あり
- 散布方法:翼による風散布、堅果は風に飛ばされるが、果鱗は果軸に残る
冬芽
- 鱗芽
- 広卵形~楕円状卵形で先はややまるい。比較的太くて短い柄あり、柄も含めて長さ1.2~1.5cm
- ヤシャブシ類との違い
- ヤシャブシの冬芽参照
葉痕
- 形:三角形
- 維管束痕:3個
用途
特記事項
- ハンノキ属の根粒菌(放線菌)による窒素固定
- ハンノキの特記事項参照
参考
- スタンダード版 APG牧野植物図:[1-1997]
- 新牧野日本植物圖鑑:[130]
- 山渓ハンディ図鑑 樹に咲く花:[1-174P]
- 山渓ハンディ図鑑 増補改訂 樹木の葉:[397P]
- “しゅんさん”の観察した静岡県の樹木:[下196]
- 観察と発見シリーズ 樹木博士入門:[‐]
- 「読む」植物図鑑:[‐]