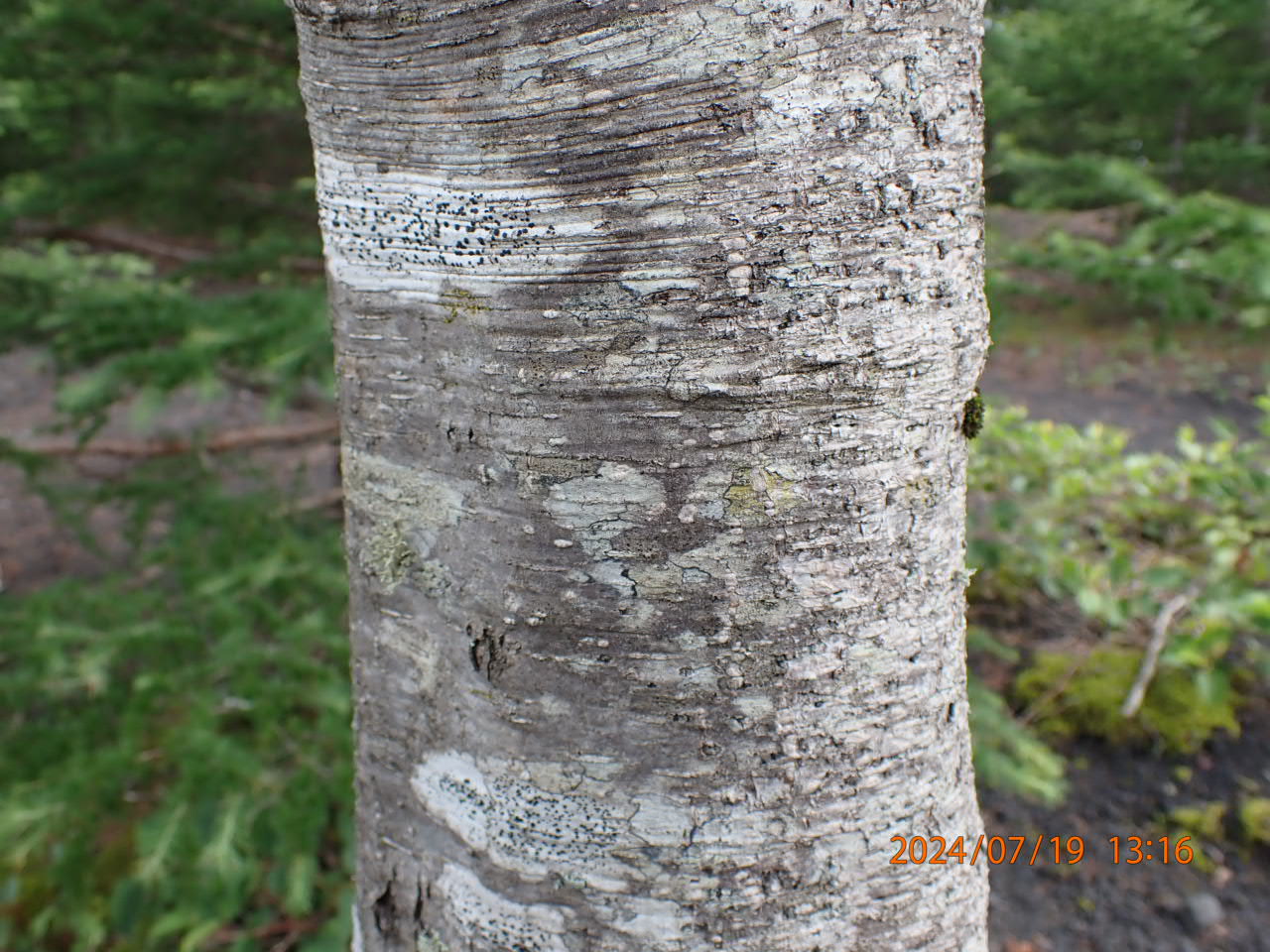基本情報
- 学名:Carpinus tschonoskii
- 科名・属名:カバノキ科クマシデ属
- 漢字名:犬四手
- 別名:シロシデ/ソネ
名前の由来
- 「イヌ(犬)」は、クマシデやアカシデよりも特徴がない説、花序の様子を子犬に見立てた説あり
- 「シデ(四手)」は、アカシデの名前の由来参照
生育地
- 山地や丘陵の雑木林に多い、人里近くでも見られる
樹形
- 落葉高木
樹皮
- なめらかで、白っぽい縦縞模様が目立つものが多い。老木には浅い割れ目が入る
葉
- 葉序:互生
- 葉形:卵形、葉身長5~9cm、葉先は短く突き出る
- 葉縁:鋭い細重鋸歯
- 葉脈:12~16対、裏面に突出
- 質感:表面はややざらつき伏毛あり、裏面は脈上や脈液に毛あり
- 葉柄:5~12mm、淡褐色の毛が密生
- 紅葉:秋に黄色に色づく
花
- 性: 雌雄同株
- 花序:
- 雄花序:前年枝に下垂、長さ5~8cm、黄褐色、苞は卵状円形で、ふちに毛あり
- 雄花:苞に1個ずつつく、雄しべ数個、葯の先にはひげ状の長い毛あり
- 雌花序:本年枝の先端や短枝のわきから下垂、苞は広卵形
- 雌花:苞の基部に2個ずつつく、花柱は紅色で先は2裂
- 花被:無花被花(花冠と萼なし)
- 開花期:3〜5月、葉の展開と同時
- 送粉方法:風媒
果実
- 種類:堅果が集まった複合果
- 形:葉状の果苞がまばらについた長さ4~12cmの果穂、果苞は長さ1.5~3cmの半長卵形、先端鋭尖、外縁に不ぞろいの鋸歯あり、内縁は全縁、基部に内側に巻いた裂片あり、果苞の基部に1個の堅果
- 色:黄/茶褐色
- 成熟期:10月頃
種子
- 数:堅果は1個
- 形:堅果は長さ4~5mmの扁平な広卵形、表面に縦の筋が10個ほどあり
- 散布方法:果苞による風散布
冬芽
- 鱗芽
- 長さ4~8mmの卵形。先端はややとがる。芽鱗は12~14個
- 頂芽は雌花序と葉が入った混芽
葉痕
- 形:半円形
- 維管束痕:‐
用途
特記事項
- クマシデ属の葉と果穂の違い
- アカシデの特記事項参照
参考
- スタンダード版 APG牧野植物図:[1-1976]
- 新牧野日本植物圖鑑:[109]
- 山渓ハンディ図鑑 樹に咲く花:[1-192P]
- 山渓ハンディ図鑑 増補改訂 樹木の葉:[400P]
- “しゅんさん”の観察した静岡県の樹木:[下198]
- 観察と発見シリーズ 樹木博士入門:[100P]
- 「読む」植物図鑑:[‐]